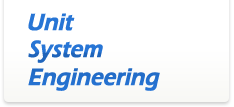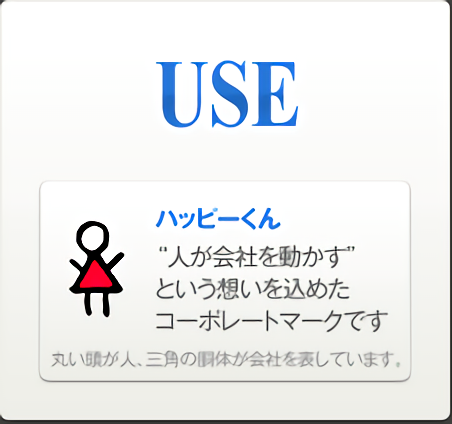新人教育カリキュラム
充実の教育で、じっくり基礎から勉強しよう。
入社後半年間は、勉強していただきます。
文系の方も心配要りません!
入社前研修(3月末)
研修カリキュラム(社外)約2日間
| 概要 |
|---|
ビジネスマナー(挨拶、名刺交換、電話対応)など、社会人としての基礎力を身に付けます |
| ある日の新入社員の研修報告書 |
3月某日 社会人としてのマナーや仕事の基本は、会社からいただいた資料に目を通していたのですが実技となると勝手が違うものばかりでした。 チームワークやコミュニケーションの講義では、ゲーム形式で行ったのですが、グループ内での面識の浅い方たちと、1つのことをするのにコミュニケーション能力がいかに重要か知りました。 次回の研修がマナーを学ぶ最後の研修なので、今日学んだことを忘れずに、しっかりと勉強し、次回に繋げたいです。 |
新入社員研修(4~9月)
導入教育(社内)約2日間
| 概要 |
|---|
|
入社当日は、基本的な社内規定などの説明を受けます。これからUSEの社員として、どのような環境で仕事を進めていくのか、実感できる日となります。
|
| ある日の新入社員の研修報告書 |
|
4月某日 入社式はとても緊張しましたが、取締役員の方々の貴重なお話は非常に勉強になり、本日から社会の一員であると改めて実感し、身が引き締まる思いでした。 社内ルールや人事制度、社内外の文書の書き方などは説明を受けましたが、全てを把握するには至らなかったので、また改めて資料や電子ファイルで確認をし、必要なときに必要なものが分かるようにしておきたいです。 会社の業務紹介は自分にはまだ理解できないことばかりでしたが、皆さんが私たち新人のためにポイントを絞って説明してくださったので、最終的に何をするものなのかは、何とか分かりました。 4月中は今日と明日の2日間しか社内の研修はないので、今のうちに業務以外のさまざまなことを吸収して学びたいです。 |
研修カリキュラム(社外)約1ヶ月
| 概要 |
|---|
|
社外の研修を受けていただきます。
|
| ある日の新入社員の研修報告書 |
|
4月某日 今回の研修は、2日間あるExcelの日程のうち、基礎編だったため問題なく進めることができました。 内容は、表作成やSUM関数、グラフウィザードを用いての作成など、学校で習ったことばかりで、今回は復習の意味合いが強く、改めてExcelの利便性や多機能さを深く知る良い機会となりました。 しかし、そればかりではなく、他のExcel関数やショートカットキーの使い方などの説明もあり、新しい知識も得ることができました。特に今まであまり活用していなかったショートカットキーは、作業効率を上げるために、この研修中に必ず習得します。 |
プログラミング基礎教育(社内)約10日
| 概要 |
|---|
|
社内の研修に入ります。
|
| ある日の新入社員の研修報告書 |
|
5月某日 今日はJavaのプログラミングについて研修を行いました。 |
OJT教育(社内)約4ヶ月
| 概要 |
|---|
|
自分の部署に配属されます。 |
| ある日の新入社員の研修報告書 |
|
6月某日 OJTの1週目は、環境構築と携帯用web工程管理システムの修正、サーブレット/JSPの勉強をおこないました。 |
10月デビュー
半年の教育を終え、プロジェクトの
メンバーとして、晴れてデビューです。
2025年度の新人教育を終えた社員の感想
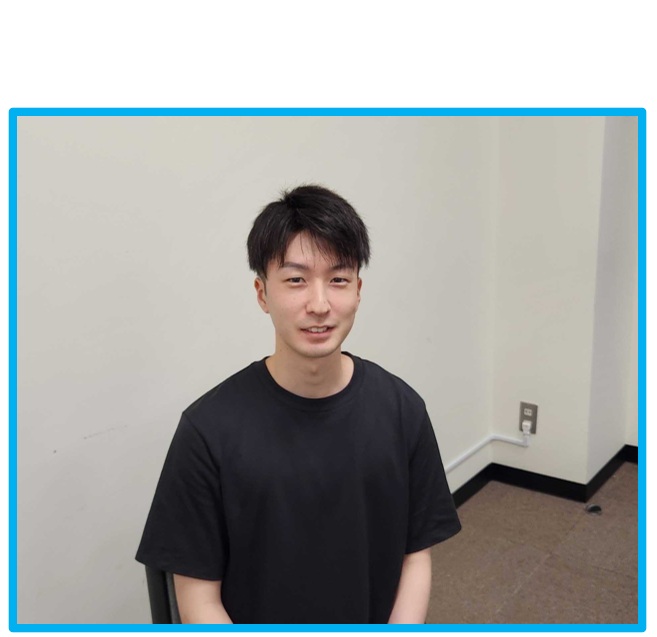
K.Sさん
新人教育を通して
2025年度の新人研修では、3月末に2日間の入社前研修を行い、そこから5月下旬までは社外での研修、そして6月から9月の中頃くらいまでは社内でのOJTといった流れで勉強をさせていただきました。
入社前研修では社会人の基礎となるマナーや電話応対の仕方、そして仕事をするうえでどのような姿勢で取り組むことが望ましいのかといったことを学びました。2日間という短い期間の中で学生気分から社会人の心意気へとグッと切り替わった印象です。
社外研修ではJavaやSQL等を用いて、プログラミングの基礎を日々学んでいました。
私は文系の大学出身でプログラミングも未経験だったため簡単な道のりではありませんでしたが、その時の苦労の一つ一つが今の自分の大きな支えになっているのを感じています。
USEに戻ってからのOJTでは実際の業務の流れに沿って設計から製造・テストまでを一通り体験させていただきました。
OJTでぶつかった壁の多くはそれまでの研修でぶつかってきたものよりも大きなものでしたが、同期社員や先輩方からのお力添えをいただいたおかげで乗り越えることができ、今まで学んできた知識の定着と社会人としての成長といった部分に繋がりました。
研修を終えた自分が実感している最も大きな収穫は、未経験からでもエンジニアとして仕事をしていくことができるという自信、そして例えこの先また壁にぶつかったとしても何度でも乗り越えることができるという自信です。
新人教育を通して手にしたこの自信と知識を胸に、これからもUSEの一員として日々精進いたします。